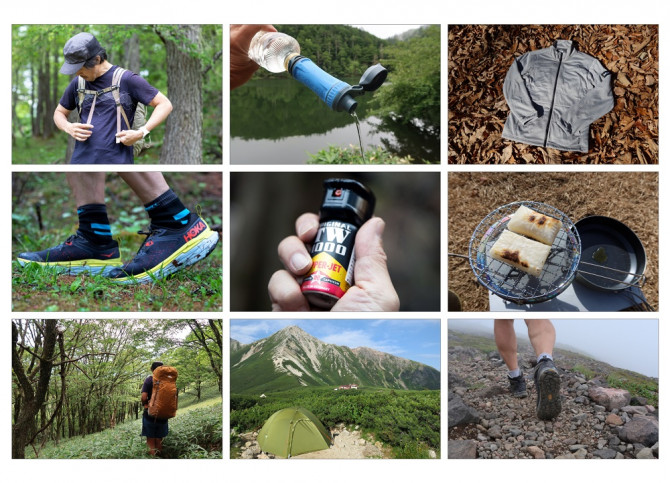かつての交易路も今は人影もまばら。奥多摩と甲州を東西に結んだ古道・丹波大菩薩道トレッキング
読者レポーターより登山レポをお届けします。上町嵩広さんは人気の大菩薩峠(だいぼさつとうげ)から静かな古道・丹波(たば)大菩薩道へ。
文・写真=上町嵩広
5月後半の初夏、奥秩父の大菩薩峠を東西に横断する旧・青梅街道にあたる古道「丹波大菩薩道」を歩いてまいりました。上日川峠(かみにっかわとうげ)を起点にして大菩薩峠を経て丹波山村へ下山する登山ルートです。

大菩薩峠・大菩薩嶺登山のメジャーな出発地である上日川峠バス停からスタートします。上日川峠まではJR中央本線・甲斐大和駅から季節運行・週末のみで路線バス(栄和交通)が走っています。
バス停すぐそばのロッヂ長兵衛横から新緑の林道を抜けて福ちゃん荘に着きました。林のなかの比較的なだらかな登りが大菩薩峠まで続きます。標高が上がってくると、それまでの広葉樹の森のなかにツガやモミなどの針葉樹も目立ち始めました。

峠までは急登といえるような部分はないのでゆったりと森歩きを楽しめました。左手に開けた稜線が見えると、その先が大菩薩峠です。峠にある山小屋・介山荘を過ぎると一気に展望が開けました。晴れていれば西に目を向けると富士山や甲斐駒ヶ岳(かいこまがたけ)などの南アルプスの山々が見えますが、この日は曇天のため眺めることができませんでした。残念・・・。


峠で一息ついて気を引き締めなおしてから東へ。大菩薩嶺へ向かうほかの登山者を背に、いよいよ丹波大菩薩道に入ります。最初はササが茂った森の斜面をトラバース気味に下っていきます。新緑の広葉樹の数も増えて緑が濃さを増します。森はカエデやブナなどが豊かで新緑が目に麗しい。秋になれば紅葉も鮮やかに色づきそうです。

しばらく道を下っていくと平地があり「ニワタシバ」との古い看板がありました。ここで交易の際に荷渡しをしていた場所であったということなのでしょう。かつてはこの道が青梅街道であり奥多摩と甲府を結ぶ交易や生活の主要道でした。その名残か、道のところどころに石組みや石段の痕跡が残っています。古道・旧道好きの方にとってもおもしろいのではないでしょうか。

丹波大菩薩道は静かな森と山歩きを楽しめました。この日は週末で大菩薩峠・大菩薩嶺の登山者で大にぎわい。上日川峠へのバスも臨時便が出るほどでした。日本百名山として登山者に大人気ですが、ひとつ脇の道に入っただけでぱたりと人影は消えてしまいます。このときに道でお会いしたほかの登山者はほんの2、3人。逆に少し寂しすぎるかもしれませんが・・・。5月にもかかわらず積み重なった落ち葉の層が登山道を厚く覆っていきます。風や人が通ることが少ないためでしょうか。


次に開けた平場である「フルコンバ」にたどり着き、ふたたび森に入ると左手に丹波山村へ、右手に小菅村へ道が分岐しています。丹波山村へのルートを進むとスギなどの針葉樹が増えて少し暗い道になりました。さらに下ると今度は「ノーメダワ」という平地に出てきました。ベンチも設置されて休憩適地になっており、ちょっとお昼休憩。
今回の山メシは「塩バニラパンケーキ」。ふわふわのパンケーキ生地の間に甘い香りのバニラクリームが挟まっています。クリームはサッパリとした味わいに塩の風味が効いており、疲れた体にちょっとありがたいです。


道標に従い丹波山方面へ再び歩き出します。小さな沢を渡り向こう側に続く道を進みます。決して沢を下らないでください。落ち葉に隠れて登山道が不明瞭なため注意が必要かもしれません。その先で「追分」という分岐点に差しかかります。東側には奥多摩の石尾根の山並みの眺望があり雲取山(くもとりやま)などを見ることができます。

追分からさらに丹波山方面へ下っていきます。しばらくすると右手に沢が出てきます。高巻きするようにつけられた道を進み、いったん沢に下りて徒渉し、また高巻きするように沢沿いの道が続きます。このあたりはけっこう大木の数が多く、深い森の雰囲気を楽しむことができました。
「藤タワ」まで下ってくれば丹波山村の集落までもう一息。ここまでの登山道に大きな難所や危険箇所などはほとんどありません。ただルートの途中に小菅村方面へ向かう分岐路や作業道などがいくつかあったので、間違えないように注意した方がよさそうです。


藤タワから三方向に道が分かれており、いずれのルートでも集落に出ることができます。今回はハイキングコースと記載のあった高尾天平(たかおてんでいろ)を経由するルートを進みます。幅の広い林道のようなルートを上がっていきますとなだらかに開けた尾根に出ます。左手に集落が見えてくると、そこからは一気に斜面を下っていき、やがて舗装道路に出て登山道は終了です。道なりに集落へ入って道の駅たばやまに到着しました。今回はここがゴールです。道の駅の前を通る国道411号線に出ればJR青梅線・奥多摩駅行きのバス停(西東京バス)もあります。
丹波大菩薩道は静かで濃密な森と山の雰囲気をゆったりと味わえる登山ルートという印象です。登山者は少ないようですが、道は荒廃していることもなく道標もしっかりと設置されているので大きな心配などはなく、全体的に歩きやすい登山道でした。(山行日程=2024年5月19日)
立ち寄った日帰り温泉
「丹波山温泉のめこい湯」

MAP&DATA
コース
上日川峠~大菩薩峠~ノーメダワ~藤ダワ~丹波山村役場前(参考コースタイム:6時間15分)

上町嵩広(読者レポーター)
登山歴は15年ほど。普段は奥多摩や丹沢周辺に出没し、八ヶ岳や北アルプスにも出張ります。好きな山は八ヶ岳の編笠山。山の抱負は「ちょっとだけ背伸びした山を登ってみる」。
この記事に登場する山

プロフィール

山と溪谷オンライン読者レポーター
全国の山と溪谷オンライン読者から選ばれた山好きのレポーター。各地の登山レポやギアレビューを紹介中。
山と溪谷オンライン読者レポート
山と溪谷オンライン読者による、全国各地の登山レポートや、登山道具レビュー。
こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- コースガイド
雨の季節は花の季節。梅雨こそ登るべき山

- 連載
- 山MONO語り
ついに登場!ライペン(アライテント)の1kg以下軽量山岳用テント ライペン/SLソロ|高橋庄太郎の山MONO語りVol.109

- コースガイド
この夏こそ日本アルプスに登ろう! 厳選アルプス入門ルート【山と溪谷2024年6月号特集より】

- その他
序章 SEA TO SUMMITが俺の登り方|「海から七大陸最高峰に登頂」をめざした理由

- ノウハウ
全国的にクマの個体数が増えている。人を襲うクマも出没するなかで、登山者がいますぐにできるクマ対策についてまとめた

- 道具・装備
- はじめての登山装備