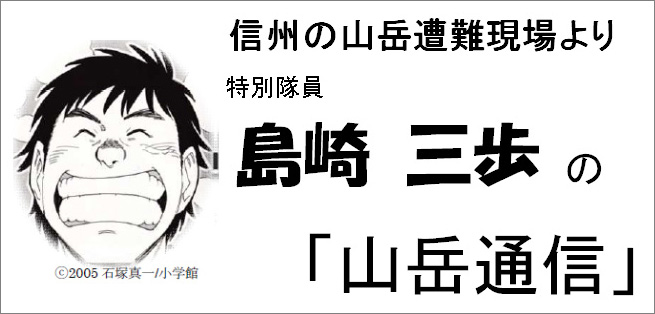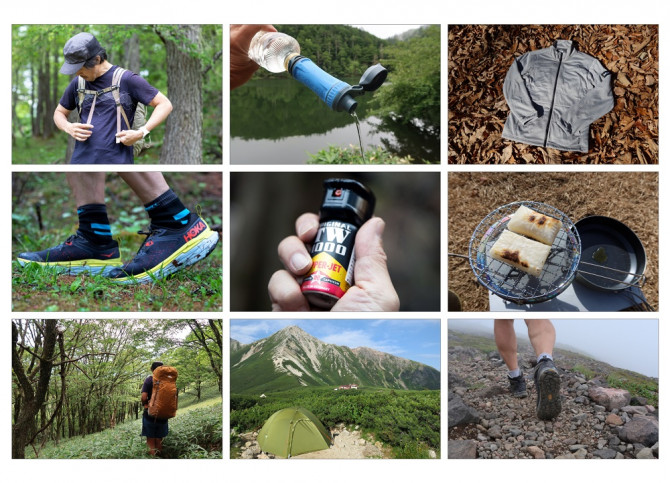知れば登れる!? 富士登山の二大リタイヤ原因とは!?
ふだん運動をしない人にとっては、かなりハードな富士登山。リタイヤしないために知っておくべき対策を紹介しよう。
文=山と溪谷オンライン、写真=PIXTA
富士登山の二大リタイヤ原因・バテと高山病
富士登山はとてもハードだ。最短ルートの富士宮ルート往復でも、山頂の剣ヶ峰までの総距離は約10km、標高差1500m。標準的な歩行時間は休憩を除いて10時間にも及ぶ。普段から登山をしている人にとってはさほど手強い行程ではないが、運動習慣のない人が10時間歩きぬくのはかなりのハードワークだ。
実際、富士山では体力を消耗してしまって登山道に座り込む人の姿は珍しくないし、中には力尽きて道ばたに寝てしまう人も。また、標高が高いことによる高山病も、富士登山を断念させる原因になっている。ここでは、二大リタイヤ原因の「バテ」「高山病」の対策について紹介しよう。
バテは「作戦で回避」する
「バテ」とは、疲労によって登山が続けられなくなってしまう状態を指す。もちろん体力不足によって起きるものだが、原因はそれだけではない。バテの原因となる登山中の問題行動とともに、バテないための回避策を見ていこう。
バテの原因①歩くペースが速すぎる
登山に慣れていない人が陥りがちなケースだ。登山口で元気いっぱいだと、張り切ってハイペースで歩き出してしまいがちだが、後から疲れが一気に出てくる。まずは準備運動で体を動かして、歩き始めは意識的にゆっくり進もう。登山中は同行者とおしゃべりできるくらいの速度が理想。息が切れて話すのがつらくなったらさらにペースダウンすること。
また、歩幅は小さく、普段なら1歩で進むところを2歩、3歩に分けて登ってみよう。また、歩を進めるときはできるだけそっと足を置くこと。ドスンという着地の衝撃は筋肉の疲労となって徐々に蓄積してしまうのだ。特に疲れが出てくると、足の置き方が雑になりがちだが、そうなると疲れは加速度的に増大してしまう。

バテの原因②水分・エネルギー不足
登山は長時間にわたる運動なので、体を動かしつづけるための水分とエネルギー補給が欠かせない。汗をかいていなくても、喉の渇きを感じなくても水やスポーツドリンクなどの水分をとるべきだ。まずは歩き出す前に300mlから500mlくらいの水分を飲んでおく。カフェインには利尿作用があるので、お茶やコーヒー、エナジードリンクなどは避けたほうが無難。水やスポーツドリンク、カフェインの入っていない麦茶などがよい。登山開始後もこまめに、少しずつ飲もう。バックパックを下ろさなくても取り出せるところに水筒やペットボトルを入れておくと、ちょっと立ち止まったときに補給しやすい。
1時間あたりの水分摂取量の目安は、体重50kgの人なら250ml、60kgの人なら300mlくらい。自分の体重と荷物の重さも足して、合計値(kg)に5mlをかけて計算してみよう。体重60kgの人が5kgの荷物を背負って6時間歩くなら、飲料を2Lは用意しておくといい。富士山の場合は途中の山小屋で飲み物を追加購入することもできる。
登山では、行動中に食べる食品を「行動食」と呼ぶ。1時間ごとに休憩をとって、すぐエネルギーに変わる糖質を含んだお菓子やエナジーバー、ゆっくり吸収されてエネルギーに変わる炭水化物が豊富なパンやおにぎりなどの行動食を少しずつ、こまめに食べよう。行動食は甘いものだけでなく、しょっぱいものも用意しておき、発汗で失われやすい塩分もとれるようにしておくといい。混雑する富士山では腰を落ち着けて食事をとるより、こうした行動食をこまめに食べ続けて歩いた方がいいときもある。ただし、高山病などで食欲がない、吐き気がするといった症状があるときは無理に食べず、水分をしっかりとるようにしよう。

バテの原因③ウェアを脱ぎ着していない
登山のウェアの重要性は別記事(富士登山、なにを着る?なにを持っていく?登山ガイドが教えます)で紹介しているが、大切なのは準備したウェアをうまく使いこなすこと。人間の体は、外気温の寒暖差に対応して体温を一定に保つために自律神経が働いているが、気温差が大きいとこの自律神経の働きが過剰になり、「寒暖差疲労」という不調を引き起こすことがある。
夏の富士山では、歩き始めの標高が低いところでは暑いこともあるし、標高が上がれば涼しくなってくる。風が吹けば寒さが増す。特に朝夕の寒さは震え上がるほどだ。1泊2日の登山の間に、体感気温がめまぐるしく変わる。だからこそ、汗をかきすぎる前にウェアを脱ぐ、体が冷えてしまう前に一枚羽織るといったこまめな脱ぎ着が重要なのだ。

高山病は「ならないこと」が大切
高山病は血液中の酸素が少なくなったときに起きる。初期症状としては
- 頭痛やめまい、もうろうとする
- 体のだるさ
- 食欲がない、吐き気
などがある。症状が軽い場合は体を温かくして、深呼吸を繰り返そう。富士登山に持って行く人が多い缶入りの酸素は、酸素を摂取することはできるものの、すぐに中身が空になってしまう。それよりは深呼吸を繰り返して、薄い空気に体を慣れさせることが大切だ。

ただし、高山病は悪化すると肺水腫や脳浮腫などを引き起こすこともあるので、症状が改善しなかったり、悪化するようならとにかく下ること。標高の低いところへ移動すれば充分な酸素を吸えるようになり、症状がおさまることも多い。
高山病は「ならないこと」、つまり予防策が大切だ。主な対策を紹介しよう。
高山病対策①水分はしっかり、トイレはがまんしない
山にはトイレが少ないからと、水分をとらずにいると新陳代謝が低下し、高山病になりやすくなる。前述の通り、水分はいつも以上にしっかりとるほうがよい。富士山にはチップ制のトイレが要所要所にあるので、小銭を用意しておき、がまんせずに利用したい。
高山病対策②標高に体を慣らす
時間に余裕をもって早めに五合目に到着し、ゆっくりお茶でも飲んでから歩き出すといい。登山開始前に五合目に1〜2時間滞在すると、体が標高に慣れた状態でスタートできるのだ。宿泊予定の山小屋に着いても、すぐに横になるのはNG。周辺を散策したり景色を眺めたりして、1〜2時間は起きていよう。眠ってしまうと呼吸が浅くなり、高山病を発症しやすくなる。
高山病対策③のんびり登山で酸欠を回避
バテの予防で触れたとおり、登山中は歩行ペースも抑えめにし、休憩はこまめにとること。体の中で酸素が不足した状態を作らないようにするのだ。息が苦しいと感じたら、歩幅をもっと小さくして、足を運ぶペースを落とす。そうすると歩くスピードがゆっくりになり、体内に取り込める酸素の量に見合ったペースにできる。
この記事に登場する山

こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- コースガイド
雨の季節は花の季節。梅雨こそ登るべき山

- 連載
- 山MONO語り
ついに登場!ライペン(アライテント)の1kg以下軽量山岳用テント ライペン/SLソロ|高橋庄太郎の山MONO語りVol.109

- コースガイド
この夏こそ日本アルプスに登ろう! 厳選アルプス入門ルート【山と溪谷2024年6月号特集より】

- その他
序章 SEA TO SUMMITが俺の登り方|「海から七大陸最高峰に登頂」をめざした理由

- ノウハウ
全国的にクマの個体数が増えている。人を襲うクマも出没するなかで、登山者がいますぐにできるクマ対策についてまとめた

- 道具・装備
- はじめての登山装備