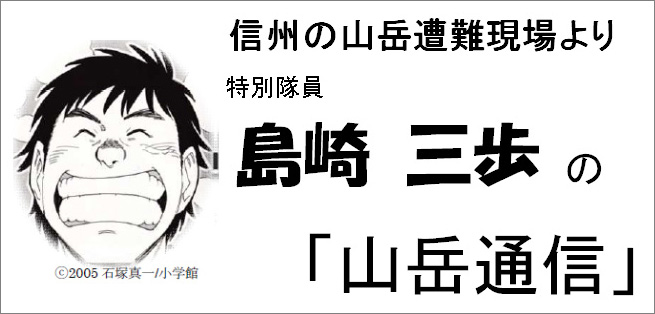富士登山、なにを着る? なにを持っていく? 登山ガイドが教えます
富士登山に必要なウェアや道具について、登山ガイドが解説する。
文=吉澤英晃、写真=中村英史
そのほかに持っていくべきもの

ヘッドランプ
手に持つハンドライトは片手が塞がってしまうので適さない。頭に装着して両手が使えるモデルを選ぶこと。明るさの目安としては、100ルーメン程度あれば充分。

グローブ
防水性があるレイングローブを用意すると雨や霧でも手が寒くなりにくい。夜間の寒さが気になるようなら、レイングローブの下に着用する薄手のインナーグローブを用意しよう。

帽子
日中は熱中症対策でハットかキャップをかぶる。風で飛ばされないようにコード付きのモデルを選ぶか、帽子とウェアを連結するハットクリップを用意するといい。夜間は耳まで覆うニット帽をかぶったほうが温かい。

ヘルメット
近年、富士登山では落石による事故が発生している。特に注意したいのが、頂上での御来光を目的とした夜明け前の行動時。日中であれば発生した落石を目視して回避できる可能性があるが、あたりが暗いと落石がどこから飛んでくるかわからない。不測の事態に備えて夜間に行動する場合はヘルメットを装着したほうが安全だ。モデルによってフィット感が異なるので、登山用の規格に通ったモデルのなかから、頭の形に合うヘルメットを選ぼう。

インナーシーツ
ほかの人が使った布団で眠ることに抵抗がある人におすすめ。薄い生地が封筒状になっており、ここに入ってから布団の中で横になる。軽量で、収納は手のひらに収まるほどコンパクト。

トレッキングポール
下りでバランスを保つときに役立つ。2本を両手に持つのが基本だが、荷物に感じるようなら1本だけ用意してもいい。使用するときの適正な長さを知り、サイズを調整する方法を学んでおこう。

サングラス
標高が高くなると受ける紫外線の影響が大きくなるため、UVカット機能があるモデルを装着する。顔のカーブにフィットするスポーツタイプがおすすめ。砂ぼこりが目に入ることも防いでくれる。

ソックス
登山靴を購入したときにはいていた厚さの靴下を用意。雨などで濡れたときに備えて予備を1セット持つ。靴をレンタルするときは厚みの異なる靴下を用意して、フィット感に応じて使い分ける。

モバイルバッテリー
携帯電話といった電子機器を充電できる山小屋もあるが、小屋によって設備はまちまちなので、バッテリー切れに備えて充電済みのモバイルバッテリーを用意する。充電用のコードも忘れずに。

ドライバッグ
特に濡れると困る着替えや替えの靴下が収まる、5~10Lくらいの防水性のあるスタッフバッグがひとつあればOK。さらに大きいサイズを用意して、そこにすべての装備を入れるのもあり。

コロナ対策に持っていくもの
感染拡大を防ぐために、口元を覆うマスク(雨や霧による濡れに備えて1日あたり2枚以上用意)や手ぬぐい、ゴミや吐物を持ち帰る密閉袋、携帯用の手指消毒剤の携行が推奨されている。
富士登山基本装備一覧
(◎=必ず持つ ◯=あると便利)
| アームカバー | ◯ | ベースレイヤーに半袖シャツを選んだときに使う。腕の日焼けを防ぐことができる |
| 替えのベースレイヤー | ◎ | 汗以外に雨や霧で濡れてしまったときに着替える。コットンが含まれているものはNG |
| レインカバー | ◎ | 雨が降ってきたときバックパックにかぶせる。バックパックと荷物が濡れるのを防ぐ |
| グローブ | ◯ | 防寒用に防水性のあるレイングローブが1セットあるといい |
| 帽子 | ◯ | 熱中症予防に。ハットは首筋の日焼けも防ぐことができる。防寒用にニット帽も用意 |
| サングラス | ◯ | 主に紫外線の影響が目を守るために着用。UVカット機能が付いているものを選ぶ |
| マスク | ◎ | 砂ぼこりから口元を守る。ネックウォーマーなどでもOK。今年はコロナ対策のためにも携行 |
| タオル | ◎ | 行動中にかいた汗を拭く。乾きやすいものなら薄手の手ぬぐいなどもあり |
| トレッキングポール | ◯ | あると登り下りがラクになる。長さを調節できるモデルが使いやすい |
| スパッツ | ◯ | 足元に装着して靴の中に雨水や砂が侵入しないようにする。パンツの裾が汚れない利点もある |
| 水筒 | ◎ | 軽いソフトボトルが人気。お湯をもらえる山小屋に泊まる場合は保温ボトルもあり |
| 水(1L) | ◎ | 行動中に補給する水分。山小屋で買い足すことができるので、用意する目安は1L |
| 行動食 | ◎ | 手軽に食べることができるパンやおにぎりなど。甘いものや塩気があるものをお好みで |
| 非常食 | ◯ | 予期せぬケガなどで予定どおり下山できない場合を想定して、行動食を1日分多く持つ |
| 地図 | ◎ | スマートフォンの地図アプリも役立つが、バッテリーを節約するために紙地図も用意 |
| 腕時計 | ◎ | 登山用でなくても問題ないが、防水性があると安心できる |
| 汗拭きシート | ◯ | 市販のシートを必要な枚数だけ密閉袋に入れて持つといい。山小屋でさっぱりできる |
| ウエットティッシュ | ◯ | ほとんどの山小屋に洗面所がない。あっても貴重な水を節約するために必要な枚数を持つ |
| ビニール袋 | ◯ | 濡れた服やレインカバーを入れる、下山時に汚れたスパッツを入れるなど、なにかと便利 |
| 日焼け止め | ◎ | 標高が高い場所は紫外線の影響が強いので男性も必須。日焼けすると疲労も蓄積する |
| スキンケアセット | ◯ | 日焼けや乾燥といった肌へのダメージをケアする |
| サコッシュ | ◯ | 山小屋の中を移動するとき貴重品などを入れて持ち運べる |
| S字フック | ◯ | 貴重品を入れたサコッシュやヘッドライトなど、よく使うものを吊るしておける |
| カイロ | ◯ | 山頂で御来光を待つとき、体を温めることができる |
| 耳栓・アイマスク | ◯ | 山小屋での睡眠・仮眠に活躍。音や明かりを気にせずに休むことができる |
| 保険証 | ◎ | ケガをすることもありうるので必ず用意。コピーでもいい |
| 現金・小銭 | ◎ | トイレの使用には100円が必要。クレジットカードに対応していない山小屋もある |
| ファーストエイドキット | ◎ | 絆創膏や常備薬など、使える範囲で必要最低限のアイテムを準備 |
| モバイルバッテリー | ◎ | コンセントが使える山小屋は少ない。主に携帯電話(スマートフォン)の充電用 |
| 携帯電話 (スマートフォン) |
◎ | 緊急時に救助を要請するなど、登山に欠かせない連絡手段。地図アプリも活用できる |
(『富士山ブック2021』より転載)
この記事に登場する山

こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- コースガイド
雨の季節は花の季節。梅雨こそ登るべき山

- 連載
- 山MONO語り
ついに登場!ライペン(アライテント)の1kg以下軽量山岳用テント ライペン/SLソロ|高橋庄太郎の山MONO語りVol.109

- コースガイド
この夏こそ日本アルプスに登ろう! 厳選アルプス入門ルート【山と溪谷2024年6月号特集より】

- その他
序章 SEA TO SUMMITが俺の登り方|「海から七大陸最高峰に登頂」をめざした理由

- ノウハウ
全国的にクマの個体数が増えている。人を襲うクマも出没するなかで、登山者がいますぐにできるクマ対策についてまとめた

- 道具・装備
- はじめての登山装備