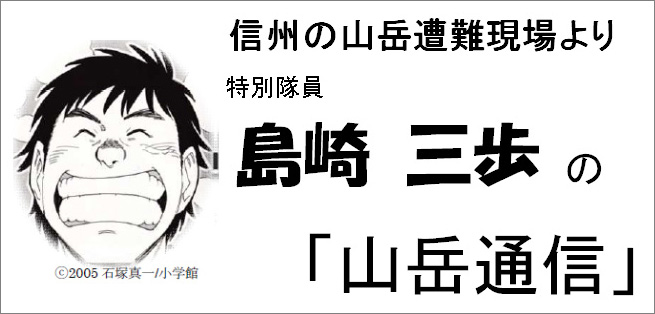富士登山、なにを着る? なにを持っていく? 登山ガイドが教えます
富士登山に必要なウェアや道具について、登山ガイドが解説する。
文=吉澤英晃、写真=中村英史
富士登山の成否はウェアと道具にかかっている!?
日本一高い山・富士山は、夏でも寒いくらいの気温というのは有名な話。でも、富士山ならいつでもどこでも寒いわけじゃなく、汗をかくほど暑いシーンだって珍しくない。登山道はよく整備されているけれど、意外に足回りのトラブルが多いのも事実。そんな富士山に登るためのウェアと道具選びについて、登山ガイドの野中径隆さんがアドバイスする。
富士山にはどんな服装で登ればいい?
日中は汗ばむ暑さ、頂上付近は真冬並みの寒さ。大きい寒暖差に備えて、役割が異なるウェアを用意します
出発時、日差しがあるとTシャツ1枚で行動できる場合もある。このときに気をつけたいのが、汗で濡れたウェアが乾いてくれないと体温が奪われ続け、低体温症に陥る危険があるということ。汗を吸って拡散蒸発を促す吸汗速乾性のベースレイヤーを着る。
一方で、2020年7~8月の富士山頂の平均気温は、最低2.2℃、最高14.9℃。これは東京と大阪の12月の平均気温に匹敵する。寒さから身を守るために、保温性のあるミッドレイヤーと保温着を用意する。雨を防ぐアウターレイヤーも必須となる。
ウェアのレイヤリングを教えてください
標高約1400〜2300m 五合目付近。登り始めは薄着でOK

天気にもよるが、晴れていて風がなければ上着はベースレイヤー1枚で充分なことが多い。パンツも1枚でちょうどいいことが大半だ。スタート時からミッドレイヤーを着る、ロングパンツの下にタイツをはくなど、重ね着しすぎるとかえって汗をかきすぎてしまう。
標高約3000m 山小屋付近。寒さを感じたらミッドレイヤーなどを重ねる

標高が上がると気温が下がるので、寒さを感じるようならベースレイヤーの上に保温性のあるミッドレイヤーや、風を防いでくれるアウターレイヤーを重ねる。薄手のウインドブレーカーを着てもいい。日差しがあれば出発時と同じ服装で行動できることもある。
標高約3500m 山頂付近(御来光時)。保温着以外をすべて着て出発

ミッドレイヤーの上にアウターレイヤーも重ねて、保温着以外のウェアをすべて着込んで行動する。耳まで覆うニット帽をかぶりグローブも装着しよう。風がある場合はネックウォーマーがあると首元が温かい。頂上で御来光を待つときは、アウターの下に保温着を着る。
この記事に登場する山

こちらの連載もおすすめ
編集部おすすめ記事

- 連載
- 山MONO語り
ついに登場!ライペン(アライテント)の1kg以下軽量山岳用テント ライペン/SLソロ|高橋庄太郎の山MONO語りVol.109

- コースガイド
この夏こそ日本アルプスに登ろう! 厳選アルプス入門ルート【山と溪谷2024年6月号特集より】

- コースガイド
富士山を「撮る」名人直伝!「夏の富士山を眺める」ポイント4つとおすすめコースをご紹介

- その他
序章 SEA TO SUMMITが俺の登り方|「海から七大陸最高峰に登頂」をめざした理由

- ノウハウ
全国的にクマの個体数が増えている。人を襲うクマも出没するなかで、登山者がいますぐにできるクマ対策についてまとめた

- 道具・装備
- はじめての登山装備